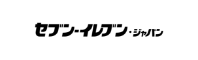Powered by Lifelong Kindergarten, Inc.
あなたの経営に、
本当に必要なものを考える。
制作会社を運営して10年。私たちはこれまで、デザインに関する様々なご相談を受けてきました。しかしその中には、デザインという手段が、必ずしも最適解とは思えないケースが数多くありました。
例えば、ある商材の海外販促用に、英語のウェブサイトを作りたいという内容。弊社で調査した結果、ネット上での取引がそもそも活発ではない分野でした。この場合、サイト開発にコストを投じる事は果たして得策と言えるでしょうか。
デザインは決して万能薬ではなく、施策の一つに過ぎません。限られた経営リソースをどこに投下するか、まずは私にご相談ください。お客様が抱えている真の課題を見極め、最適な解決策をご提案いたします。

早稲田大学文化構想学部卒業。フジテレビ報道局からSMBC日興証券へ入社。2016年デザインコンサルティングファームLifelong Kindergarten,incを設立。(株)yuiおよびfamilog(株)の設立に参画。コンサルティング、開発全てのPMを務めながら、複数社の経営を行う。
Clients
and more
Works
-

リクルートR&Dスタッフィング
-

セブン-イレブン・ジャパン 採用
-

Spread
-
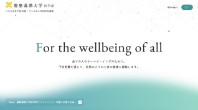
慶應義塾大学医学部|ヒルズ未来予防医療・ウェルネス共同研究講座
-

TAKAOKI ONISHI
-

LOTTE VENTURES JAPAN
-

P style
-

Crown Data
-

THREE
-

WOJE
Creative Team
クリエイティブ業務における品質向上と速度維持のため、外部委託も含めた分業制を採用しています。作業単価の異なる人材を多く抱えることで、ご予算に合わせたご提案を可能にしています。また、プロジェクトの進行管理、デザインの監修は社内のディレクターが行います。
-
Designer
28名 -
Coder
19名 -
Engineer
47名 -
Marketer
3名 -
Photographer
12名 -
Sales
5名
-
Director
堀内 祐輔
演出家 菊池久志に師事を経て独立。自身の映像の企画から、演出、撮影、編集を行う稀な制作スタイルで、クライアントの意図をできる限りこぼすことなく適切な視覚表現、構成設計の提案も行う。
-
Director
阪口 麻衣子
夢展望株式会社でWebデザイナー、株式会社i-neでブランドディレクターを務め、その後LLKに入社。ブランディング案件におけるデザイン、ディレクション、マーケティング等幅広く担当。
-
Director
植村 拓矢
LLK設立から参画し、2017年同社役員就任。数多くの制作案件を手がける。グッドデザイン賞の他、複数のコンテストで受賞。2023年、プロデューサーを務めた短編映画が複数の国際映画祭にノミネート。
Partnership
-
 Strategy Consultant
Strategy Consultant韓 景旭
株式会社Nofty
早稲田大学卒業。米系コンサルティング会社のアーサー・ディ・リトル・ジャパンにて大手製造業を中心に新規事業や新製品の立ち上げプロジェクトに従事。ロボット開発ベンチャーにて知財やマーケティングなどを担当後、韓国SaaS企業にて日本事業を担当後に起業。韓国大手VCの日本担当など、海外企業の日本進出や日本企業と海外企業の提携に強みを持つ。
-
 Financial Strategy Consultant
Financial Strategy Consultant四辻 弘樹
早稲田大学卒業。SMBC日興証券投資銀行部門・みずほ証券グローバル投資銀行部門においてM&A、ファイナンス、IPO、IR等に携わる。その後は上場ITベンチャーにおいてCSOとして企業戦略、M&A、IR、事業開発に従事。現在はM&A専門家の他、資金調達支援、IPO支援など社外CFO・CSOとして活躍。
-
 M&A Consultant
M&A Consultant徳丸 祐也
株式会社M&Aベストパートナーズ
大学卒業後、大手証券会社にて、個人富裕層及び法人の資産運用業務に従事。その後、大手M&A仲介会社へ転職。製造業界、医療業界を中心に建設、不動産業界のM&A案件を担当。これまでに50社以上のM&A成約に携わる。
-
 Marketing Strategy Consultant
Marketing Strategy Consultant林 幸一郎
Steelstyle株式会社
早稲田大学卒業後、株式会社阿波銀行に入行し融資・渉外業務に従事。その後Webコンサルティング会社を経て、運用型インターネット広告を専門に取扱うアナグラム株式会社に参画。中小企業から資金調達後のスタートアップ・上場企業まで、業種を問わず様々な会社のプロジェクトに携わる。
-
 Human Resources Consultant
Human Resources Consultant市原 孝志
株式会社Crewto
WEB制作事業に凡そ18年間携わり、コーポレートサイトからショッピングサイト、WEBサービス、アプリ開発など幅広いクリエイティブのディレクターを経験。起業前に従事していたクックビズ社においては新規事業立上げメンバーとして参画し、開発/運営に従事。未来に残す価値のあるサービスを手がけたいという思いがあり、一緒に仕事をしてきた仲間と共に「Crewto」を創業。